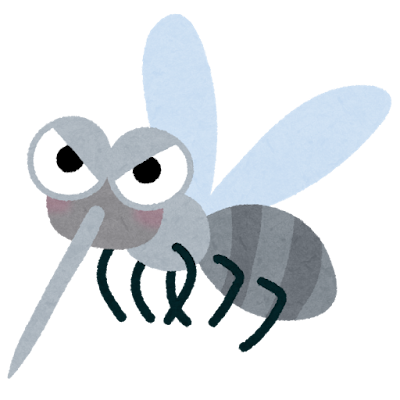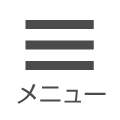お知らせ・ブログ
Blog2024.01.20(土)
先日は雪が降ったりと とても寒い日々が続いておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
今回はこの寒い時期こそ注意したい病気について紹介します。
〜泌尿器疾患〜(特に尿路閉塞)
寒さの影響で、冷たくなった水を飲まない、動きたくないなどにより 飲水量が低下します。その結果、結石・膀胱炎・尿路閉塞などの泌尿器のトラブルが増えてきます。特に雌猫は膀胱炎、雄猫ちゃんは尿路閉塞が多く、閉塞すると数日で重症化してしまうとても怖い病気です。
頻尿、血尿などの症状が見られ、ひどくなると食欲不振や嘔吐などの症状が現れますので、早めの受診をお勧めします。過去のブログでも取り上げていますので、読んでみて下さい。
飲水量を上げる工夫として、こまめに水をかえる・水飲み場を増やす・特に寒い時期は温水をあげるなどがありますので是非お試しください。
*猫ちゃんの尿道閉塞について (ブログ)
〜関節疾患〜
寒さの影響で運動量の低下や筋肉のこわばりがある状態から急に運動すると、それがきっかけで関節炎を起こすことがあります。また、関節や骨に持病を抱えている子は、この時期に症状が悪化することがあると言われています。
症状としては、急に庇うよう歩く(跛行)、じっとして動けない、足を触ると怒るなどが挙げられます。
~呼吸器疾患~
冬にインフルエンザやノロウイルスが流行するように、低温・乾燥によって喉や鼻の粘膜のバリア機能が落ち、犬猫もウイルス性の呼吸器疾患にかかることがあります。特に子犬のケンネルコフは慢性化すると根治が難しくなるため注意が必要です。
咳やくしゃみ・鼻水・目ヤニなど風邪症状が主ですが、悪化する場合は早めの受診をお勧めします。
~皮膚疾患~
乾燥によって皮膚のバリア機能が落ち、体の痒みや皮膚炎を起こすことがあります。また、こたつ・ストーブなどの暖房器具による低温やけどもこの時期気をつけなければいけません。しかし、普段からアトピー性皮膚炎に悩まされている子は、この時期、花粉や昆虫といった環境アレルゲンが減る時期ではあるため、痒みが落ち着く子もいます。
肌のカサカサが気になる子は、わんちゃん用の保湿剤を使ってみてください。当院でも販売しています
お正月も過ぎてつい気が緩んでしまいがちですが、健康に気をつけて生活して頂けたら幸いです。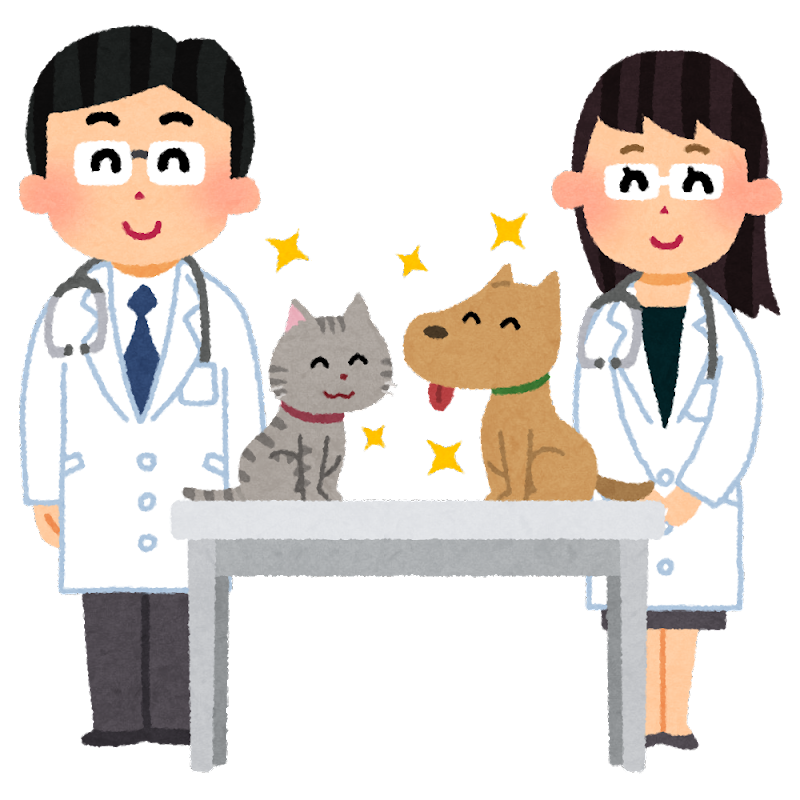
2023.11.25(土)
少し前までまだ夏の面影があった日も多かったものの、ここ最近はぐっと冷え込むようになりましたね。
こんな冷え込む日は、ワンちゃんやネコちゃんの体温が心地よく抱っこする時間が長くなっている今日この頃です。
さて、今日は「ノギ」についてお話しようと思います。
みなさま、ノギってご存じでしょうか?
先日、足先の傷がなかなか治らないボーダーコリーのワンちゃんが来院されました。
傷自体はそこまで大きくないのですが、腫れと赤みがひかず腫れているところを押すと傷から膿が出てくる状態でした。

抗生剤や洗浄治療での治りが悪いため、膿が出てきている穴を辿り何か原因がないかをチェックすることとなりました。
穴を辿り状況によっては広く皮膚を切る必要があるので、全身麻酔での処置となります。
20kg程度の大きめのワンちゃんでしたが、なんと元の傷の約6~7cm上の方まで穴が続いており、その元にはノギという植物が異物として入り込んでいました!

足の皮膚の奥深くから取り出した実際のノギです。
ノギとは、イネ科の植物の穂の先にある0.5~1.0cm程の刺状の突起のことを言います。
このイネ科の植物はどこにでも生えている雑草です。
ワンちゃんは草むらの中の探検が大好きなので、このノギが足先に刺さった場合には今回のようにどんどん奥に入り込んでしまい、異物となります。その場合、足先の傷が治らない原因となります(ノギを取り除かない限り治りません!)。
このワンちゃんは、かなり大きく皮膚を切開した為飼い主様も治りを心配されていましたが、
ノギを取り出し2週間でここまで改善しました!

外見からはノギが入り込んでいるのは全く見えないため、怖い植物ですよね・・・。
他にも、わんちゃんが鼻先で草むらの中をクンクンすることで、ノギが眼や耳の中に入ってしまう事もあります。
眼や耳の中に入った場合には、急な痛みを伴います。
お散歩後に急に眼や耳をすごく気にするなどがあれば、すぐに病院にご連絡下さい!
2023.03.07(火)
寒気も少しずつ緩み始めましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
本日は、愛犬愛猫たちのご飯の悩み、食べムラについてお話ししようと思います。
私たちが診察時によく聞くお悩みとして『昨日まではメインのカリカリフードを食べていたのに急に食べなくなった』 『おやつのチュールはよく食べるのに…』などのご飯のお悩みが少なくありません。
では、食べムラにはどのような原因が考えられるでしょうか。
・飼い主様が食事以外にオヤツなどを与えすぎて 肝心の食事前に満腹になる
・運動不足により食欲が湧かない
・おやつが好き・ヒトの食べているものに興味がある
・食欲低下を発現するような強いストレスにある
・身体的疾患がある(病気で食べられない) など
動物たちは『総合栄養食』と書かれている市販食や手作りで作るオーダーメイドのご飯を食べていれば、基本的に栄養不足にはなりません。しかし、おやつや ヒトのご飯は彼らにとって未知かつ美味しいので、それに慣れてしまうと元のご飯に戻すのが難しいこともあります。おやつはコミュニケーションの道具として与えるようにしましょう。
また、運動不足によって1日の必要エネルギーが落ちるとご飯を残す子もいます。適度な運動は動物にとっても大切ですので、お散歩やおもちゃを使って思いっきり遊んであげてください。
しかし、1番心配なのは『病気で食べられない』ことです。年齢やご飯に飽きたなどの原因で食欲が低下することもありますが、続くようなら一度診察にいらして下さい。
最後に、2月よりワンちゃん達の健康診断(血液検査)が普段よりお手頃にできるようになっています。ご興味のある方は、フィラリア予防の診察時にご相談ください。
2022.06.08(水)
少しずつ気温も上がりそろそろ梅雨に入る時期ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
本日は、わんちゃん猫ちゃんの歩行異常についてお話しします。
歩行異常とは、足を引きずって歩くびっこの状態『跛行』や足を浮かせてしまう『挙上』、
足が上手く動かない『麻痺』など、歩き方がおかしい状態を指します。
原因は、大きく分けて
・爪が折れる、異物が刺さるなどの外傷
・関節炎や靭帯の異常などの整形疾患
・椎間板ヘルニアなどの神経疾患
などの事が多いです。
しかし、ときに複数の病気を併発していたり全身性の病気に伴う場合もあり、
血液検査やCT・MRI検査、関節液検査など更に詳しい検査が必要になることもあります。
ご自宅のわんちゃん猫ちゃんの歩き方に違和感を感じる場合には、獣医師にご相談下さい。
診察にいらっしゃる際には、携帯電話などで歩き方の動画を撮ってきていただけると分かりやすい場合があります。(可能であればで大丈夫ですよ~)
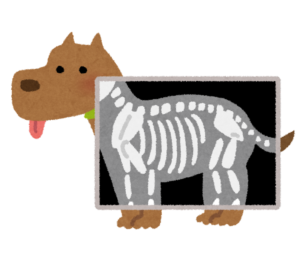
続いて、普段からお家できるケアをいくつか紹介します。
まず、体重管理です。体が重いわんちゃん猫ちゃんは体を支えるために
関節や骨により負荷がかかってしまいます。特に大型犬で体重が重い子達は注意が必要です。
次に、お家で滑らない床を作ってあげることです。
特に中高齢のわんちゃんは、足を滑らせたことによって急に靭帯を切ってしまうこともあります。
フローリングの床のお家はカーペットを敷いてあげたり、こまめに足裏の毛や爪を切る事も一つのケアになります。
わんちゃん達は飼い主さんが気付きやすいサインを出してくれる子が多いですが、
猫ちゃん達は気付かないうちに足腰が弱っている子も多いと言われています。
なんと猫ちゃんは、10歳を過ぎると10頭中9頭が関節炎になっているとの報告もあります。
普段の生活のなかで、段差の登り下りや爪研ぎをあまりしなくなったなどがみられましたら
関節炎のサインかもしれません・・・!
気になる様子があれば、お気軽に獣医師にご相談下さい。
また、若いうちからでも関節をケアできるサプリメントもありますので、気になった方はぜひスタッフにお尋ねください!

2022.05.01(日)
みなさまゴールデンウィークをいかがお過ごしでしょうか。
おうちのわんちゃんの狂犬病予防注射やフィラリア症の検査で病院にいらしていただく時期となりました。
そこでフィラリア症について改めてお伝えさせていただこうと思います。
フィラリアとはわんちゃんの血管に住み着く寄生虫です。
心臓から肺へと血液を送る部分の血管に成虫は住み着きます。
住み着いた成虫は雌雄で増えることも雌だけで増えることもできます。
このフィラリアの幼虫は非常に小さく、血液とともに全身を回っており
蚊の吸血によって犬から犬へと移っていきます。
フィラリア症の検査では、この幼虫が血液中にまぎれているか否かを確認しております。
フィラリア症は放置しておくと血管や心臓に虫が詰まってしまい、命に関わる状態になってしまいます。
首都圏ではみなさまの予防のおかげで発生は少ないですが、日本全体ではまだまだ危険性の高い病気です。
フィラリアの予防薬には、オヤツ感覚で食べられるタイプや、錠剤、首に塗るタイプなどの種類があります。
また、フィラリアだけでなくノミダニも一緒に予防出来るオールインワン製剤もあり、ひとつで全ての予防が出来るのでおすすめです。
一度ノミが身体についてしまうとお家の中でも繁殖してしまうため駆除が大変です。
更に、ノミやダニからうつってしまう病気もあるため(なんとヒトにうつる病気も!)、ノミダニ予防も忘れずにしっかりしましょう。
ワンちゃんの種類や性格によっては、より最適な予防薬がある場合があるので
どれが良いのか分からないわ・・という方はお気軽にスタッフまでお尋ね下さい。