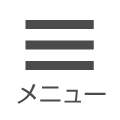お知らせ・ブログ
Blog2020.10.21(水)
だんだんと冬の気配が近づいてきましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
昼夜の寒暖差が激しいですが、季節の変わり目に体調を崩すのは人だけではありません。どうぶつたちもこの時期は体調を崩すことが多いのでよく様子を見てあげてください。
さて、本日は犬や猫の認知機能不全症候群(認知症)についてのお話をしたいと思います。以前も投稿した記事より引用しておりますので、ご存じの方も多いかもしれません。
最近では獣医学の進歩により犬や猫の寿命が延び、それに伴っていわゆる生活習慣病や、認知機能障害も増えています。
特に犬は、人間や猫と違ってすべての個体で認知機能障害になる素因があると言われています。特に犬種や性別による差はなく、高齢であることが引き金になります。もちろん猫にも認知症が認められており、高齢であるほどリスクは高まります。(犬で15-16歳以上の70%、猫で15歳以上の50%でなんらかの認知機能低下があると言われている)
認知症に関しては人と同様に予防することが重要と言われていて、発症後に治療したらすぐによくなるというものではありません。是非早い段階で予防・対策をとってあげてください。
最近では脳の酸化(老化)に対するサプリメントやフードがあるので、ご興味があれば是非スタッフまでお声かけください。7,8歳から始めるといいと言われています。
そもそも認知機能障害は、人間だと言葉を交わすので気づきやすいですが、喋らない犬や猫の場合はどうやって気づいてあげれば良いでしょうか?
当院では認知機能障害発見のチェックリストを用意しておりますので、ご興味のある方はお声かけください。その症状は、病院ではなくおうちで気付くことがほとんでです。
(犬の認知症のチェックリストはこちらをクリックでダウンロードできます。)
症状の例としては、普段楽しく遊んでいたことをやらなくなってしまう、慣れている道を忘れてしまう、家族の顔を忘れてしまう、昼夜逆転してしまう、などです。日常生活でよく観察していると気づく変化ですので、普段からよく見ていてあげてください。
また、夜鳴きや夜間の徘徊、そそう(トイレを忘れてしまう)など、わかりやすい変化も症状の一つです。
以上のような変化が見られたら、また気になる行動がありましたら、是非ご相談ください。
では実際、認知機能障害になってしまったとき、おうちではどういった対策をとれば良いでしょうか。
認知機能障害にとって、ストレスは悪化の要因になります。何か粗相(そそう)をしても、絶対に叱らないであげてください。
また、トイレに行きたいけれど行けない、歩きたいのに歩けない、という葛藤もストレスになります。段差をなくす、トイレまで歩く筋力が落ちてしまっているのであればトイレを近づけてあげるなど、環境を整えてあげてください(環境エンリッチメント)。
徘徊をしてしまう子は狭い場所に引っかかって出られなくなることがあります。柵をつけるなど、怪我をしない対策もとってあげてください。
また、お散歩も効果的です。いい刺激は認知機能障害の進行をゆっくりにします。筋力が落ちてしまっても、ゆっくりでいいので外の空気を吸わせてあげてください。知育トイや頭を使った遊びもお勧めです。
あまり症状が強い場合は投薬が必要になる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
また、認知機能障害ではなく病気であることもあります。例えば、膀胱炎からそそうをしてしまったり、体に痛みがあり鳴いてしまったすることもあるでしょう。気になる症状がありましたら、必ず診察を受けるようにしてください。
高齢になって夜鳴きや徘徊が問題行動となるケースが増えております。ぜひ予防してあげましょう。
2020.08.13(木)
まだまだコロナの猛威は収まりそうになく、外出自粛、テレワーク、イベントごとの中止などが続き、ストレスを感じている方も多いのではないでしょうか。
人はストレスを感じると体に様々な不調をきたしますが、多くの方はお腹を壊して、下痢になってしまうのではないでしょうか。
外出自粛が求められる中、家の中でストレス発散できることをこの機会に見つけるのもいいかもしれませんね。
さて、それではワンちゃん、ネコちゃんはどういったときに下痢をするのでしょうか。
ワンちゃん、ネコちゃんが下痢になる原因は極めて多く、軽症で済むものから重い病気の症状として現れるものまで様々です。
そのため下痢をしたという情報だけでは私たち獣医師も何が原因なのかわかりません。そこで重要なのが飼い主様から得られる情報です。
うんちの様子、量や回数はどうであるか、血は混じっているのか、しぶり(うんちをしようとするが出ない様子)、体重の変化、元気食欲はあるかなどの情報が得られると診断がつきやすくなります。
また病院では身体検査を行い、必要に応じて、糞便検査、血液検査、内視鏡検査などを行います。
下痢の多くは軽傷で済みますが、中には重症なものもありますので、おうちのワンちゃん、ネコちゃんが下痢をしていたら、まずは病院にいらしてくださいね。

2020.07.28(火)
今年はコロナの影響でマスクが手放せませんね。思わず咳をしてしまうと周りの視線が痛いです。
うちの子が最近咳をしていて、もしかしてコロナにかかったかも、と不安を抱く飼い主様も多いかもしれません。
ワンちゃんネコちゃんに関しましては、まだまだ詳しいことはわかっていないので、リスクの高いところへの外出等は人と同様、なるべく避けたほうがいいかもしれません。
さて、ワンちゃんネコちゃんが咳をすることの一般的な原因としては上部気道(口、喉、気管)の問題、肺の問題、心臓の問題の3つに分けて考えることが出来ます。
検査としてはコフテストと言って気管を刺激することによって咳を誘発する簡単なものから、レントゲン検査、心臓のエコー検査などがあります。
レントゲン検査では気管の虚脱(空気の通り道がつぶれる)があるかどうか、肺炎などが起きているかどうか、心臓が大きくなっていないかどうかなどを診ます。
心臓が大きくなっていたとしたら、より詳細に心臓のエコー検査を行い、心臓に問題がないかどうかを確認します。
それぞれの問題によって治療内容も変わり、命の危険が伴う問題のこともあります。
最近うちの子がよく咳をするなと思ったら、まずは診察にお越しください。

2020.07.05(日)
もうそろそろ梅雨もあけ夏も本番、蒸し暑い日が多くなっていますがいかがお過ごしでしょうか。
私ごとですがここ1年程で5~6kgの減量に成功しまして、痩せたねと最近声をかけてもらえる事が増えてひっそりとホクホク喜んでおります。
私は無類のお菓子好きなので、ダイエットの為お菓子を減らす事は断腸の思いでした(少し減らす程度で、全くやめられません……)。
わんちゃんやねこちゃんにもウルウルとした瞳でおやつやご飯をねだられると、ついあげたくなってしまいますよね。
おやつをあげる事はとても良いコミュニケーションになりますが、ついあげ過ぎてしまうとわんちゃんねこちゃんも肥満になってしまいます。
実は肥満は慢性的な軽度の炎症とされており、多くの病気に関連していると言われています(体重過多の犬の寿命は平均で2年短いという報告も…!)。
ポテっとしたお腹やプリプリとしたお尻も可愛いですが、わんちゃんねこちゃんの為にも適正な体型を保つ事は大事です。
さてここで、わんちゃんねこちゃんにも適正な体型基準がある事をご存知ですか?
よく診察中に何kgくらいが良いですか?と聞かれる事が多いですが、体重はあくまで目安。個体差もあります。
そこで、1匹1匹のわんちゃんねこちゃんの体型を判断するのに使われているのが、「ボディーコンディションスコア(BCS)」です。
わんちゃんねこちゃんの体型を目視(横、上の2方向)と触診によって9段階で評価します(5段階のものもあります)。
理想的な体型は、肋骨が触って分かる程度の脂肪、上から見ると腰にくびれがあり、横から見るとお腹のへこみが分かる体型です。

ご自宅のわんちゃんねこちゃんの体型、いかがでしょうか?
毛があるため見た目よりも実は太っていたり痩せていたり…なんて事も多いです。
一度体型を意識しながら、ご自宅のわんちゃんねこちゃんを見て触ってみて下さい。
いまいち分からないわという方はお気軽にスタッフに聞いて下さいね。

2020.06.13(土)
春も過ぎてコロナ騒動も少し落ち着きつつありますね。しかし、まだまだ油断は禁物なので3密対策、マスク装着、うがい、手洗いにみんなで努めていきましょう。
6月に入り、暑い日が多くなってきましたが、そんな日は風呂上がりのビールがより最高に感じられます。でも、ついつい飲み過ぎるとトイレが近くなりますよね。
犬猫にも似たことが起き、それを多尿多飲と言います。
お皿に入っている水の減るスピードがはやくなった、水をがぶ飲みするようになった、おしっこが多くなった、寝ているときにおもらしをするようになった、そんなことが気付きのヒントになります。
これには大きく分けると
- 水をよく飲むから、おしっこが増える (多飲からの多尿)
- おしっこが増えるから、水をよく飲む (多尿からの多飲)
上記の2タイプがあります。
前者は脳や精神的な問題で水を飲まずにはいられない状態、または塩辛い食べ物を食べているから喉が渇くなどがあります。
後者は全身の様々な病気によって引き起こされ、命に関わる重大な病気が潜んでいることがあります。多くの多尿多飲はこちらのタイプです。
一般的な基準としては1日当たり犬:100ml/kg以上、猫:60ml/kg以上の飲水がみられるようなら多飲と判断され、これに近い場合も多飲を疑います。
原因を知るために、尿検査、血液検査、ホルモン検査などの検査を組み合わせて行っていきます。
もし多尿多飲の症状が見られた場合は、もう、いつまで水飲んでるの!没収!なんてことはやめましょう。原因によっては脱水症をおこすことがあるため、水を飲ませることを我慢させないで下さい。簡単な説明にはなりましたが、多尿多飲の症状がありそうだ、いやあるね、という場合には当院スタッフへ気兼ねなくご相談ください。